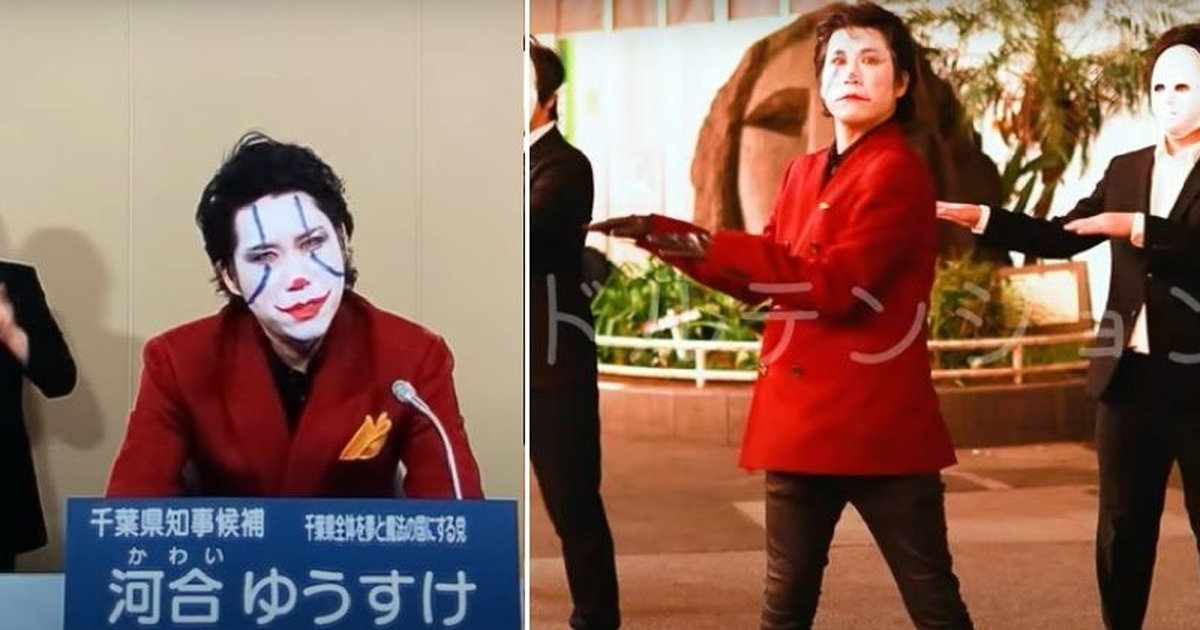日本にインフレが戻ってきました。 今年、日本の消費者物価指数は4.3%まで上昇し、過去30年間で見られなかった水準となった。 ほとんどの国ではインフレは一般に容認できませんが、日本では物価の上昇は長期にわたるデフレ状態から脱却するための重要なステップとなります。
CPIの上昇は、支出と需要の増加を特徴とする経済がより活況になっている兆候である可能性があることが示唆されています。 これはひいては、より回復力のある持続可能な成長軌道への移行の兆候となる可能性があります。
つまり、インフレの加速は、日本銀行(日銀)の政策形成においても大きな課題となっているのです。 国際通貨基金(IMF)の副グループリーダー兼シニアエコノミストのJinho Choi博士と、チームリーダー兼チーフエコノミストのJae Young Lee博士によれば、日銀は経済成長の刺激と経済成長との間の微妙なバランスを取るために慎重に舵を切る必要があるという。価格の安定を確保します。
7月28日、日銀は国債利回りの上限を緩和することで、超緩和政策から小さいながらも重大な後退をとった。 しかし、日銀はまた、物価が安定して持続的に年間約2%上昇していることが保証されるまでガイダンスは変更しないと主張し、そのことも明確にしている。
生鮮食品価格を除いた日本のコアCPIは、2022年4月以来中央銀行の目標水準を上回っている。しかし、日銀は現在の政策設定の調整に伴う便益とコストについて引き続き警戒している。
日銀の段階的なアプローチは、将来のインフレ見通しを巡る不確実性に根ざしている。 ASEAN+3マクロ経済調査局(AMRO)によると、6月の日本のコアCPIは17カ月ぶりに4.2%に低下したが、依然としてピークに達しており、おそらく今年は平均して3%程度、来年は2%程度になるだろう。
しかし、IMFの専門家らによると、日本のインフレ動向をめぐる不確実性を考慮すると、日銀が慎重なアプローチを維持するのは正しいという。 しかし同時に、銀行は、高インフレが続く兆候が現れた場合には、異なる立場に陥ることを覚悟しなければなりません。
世界的な食料価格とエネルギー価格の高騰により、日本のインフレ率は他の先進国よりも遅く、2022年の第2四半期に大幅に加速し始めた。 円がドルに対して急激に下落し、それが日本の輸入物価の上昇を増幅させた。
2022年末以降、インフレ情勢にはもう一つの注目すべき変化があった。 世界の原油価格は下落したが、円はここ数十年で見られなかった水準まで下落した後、比較的安定を保った。 その結果、日本の輸入価格は大幅に下落した。
しかし、主に非エネルギー製品やサービスの価格上昇により、日本では今年コアインフレが加速した。 しかし、このような価格上昇が経済に浸透するまでに時間がかかることは珍しいことではありません。 実際、AMROは円が10%下落すると消費者物価が上昇するまでに最大9カ月かかる可能性があると試算している。
日本のインフレ率の高止まりを支えるには、いくつかの重要な要因が重要な役割を果たす可能性があります。
まず、賃金上昇率の動向が重要な役割を果たすだろう。 今春の賃金交渉は、何十年も停滞していた賃金がついに上昇する可能性がある兆候を示している。
大企業は大幅な賃上げを行っており、3.9%という過去31年間で最大の賃上げとなった。 これは、従業員が生活費の上昇に対処する必要があることを雇用主が認識していることを示しています。
しかし、今年の大幅な賃金上昇が来年か再来年まで続くと信じる理由はほとんどなく、賃金上昇が高インフレの定着した要因となるかどうかという問題は未解決のままである。
日本企業による投入コストの転嫁も、インフレ情勢におけるもう一つの重要な要素となるだろう。
日本企業、特にサービス業の企業は伝統的に消費者向けの価格引き上げに消極的だ。
しかし、最近では、原材料費や人件費の高騰が顧客に与える影響が増大しています。 4月の日本のサービス価格は前年同月比1.7%上昇し、消費税増税の影響を受けた2つの価格帯を除くと1995年以来最大の月間上昇率となった。 。
現在のインフレ環境の上昇により、日本企業はコストをカバーするためにより積極的な値上げを余儀なくされる可能性があり、インフレ見通しの下振れリスクとなる可能性がある。
最後に、供給側の要因によるインフレの急増を考慮する必要がありますが、これらの影響は一時的なものである傾向があります。
IMFの専門家らによると、輸入価格の上昇が国内のインフレやインフレ期待に与える影響を注視する必要がある。 継続的な地政学的な緊張により供給に一時的な混乱が生じ、エネルギー価格がさらに上昇する可能性があります。 さらに、日米間の金融政策の相違が続いていることを考慮すると、急速かつ頻繁な円安が国内のインフレをさらに加速させる可能性がある。
日本のインフレ動向を取り巻く重大な不確実性を考慮すると、日銀は、これまで以上にインフレ率が上昇する環境を特徴とするパンデミック後の「新常態」の出現に備える必要がある。 。
専門家らは「長期的な見通しと世界経済の不確実性を考慮すると、日銀は金融政策の枠組みの包括的な評価に着手する際には細心の注意を払うべきだ」と勧告した。 。
過去10年間に何が起こったかを考慮すると、日銀は政策調整をより明確に発表した後、より柔軟な選択肢を模索する必要がある。 特に、日銀は2%という長期インフレ目標が国内の根底にある価格設定行動と一致していない可能性があることを認めることを検討する可能性がある。
「より実践的かつ現実的な目標を達成するために、日銀は1%から3%の物価安定目標レンジを採用することを検討することができるだろう。 これにより、中央銀行は金融政策をより柔軟に実施できるようになる。 世界環境の不確実性が続く中、日銀は適応できなければならない」と専門家は強調した。

“Web Specialist. Social Media Ninja. Amateur Food Enthusiast. Alcohol Advocate. General Creator. Beer Guru.”