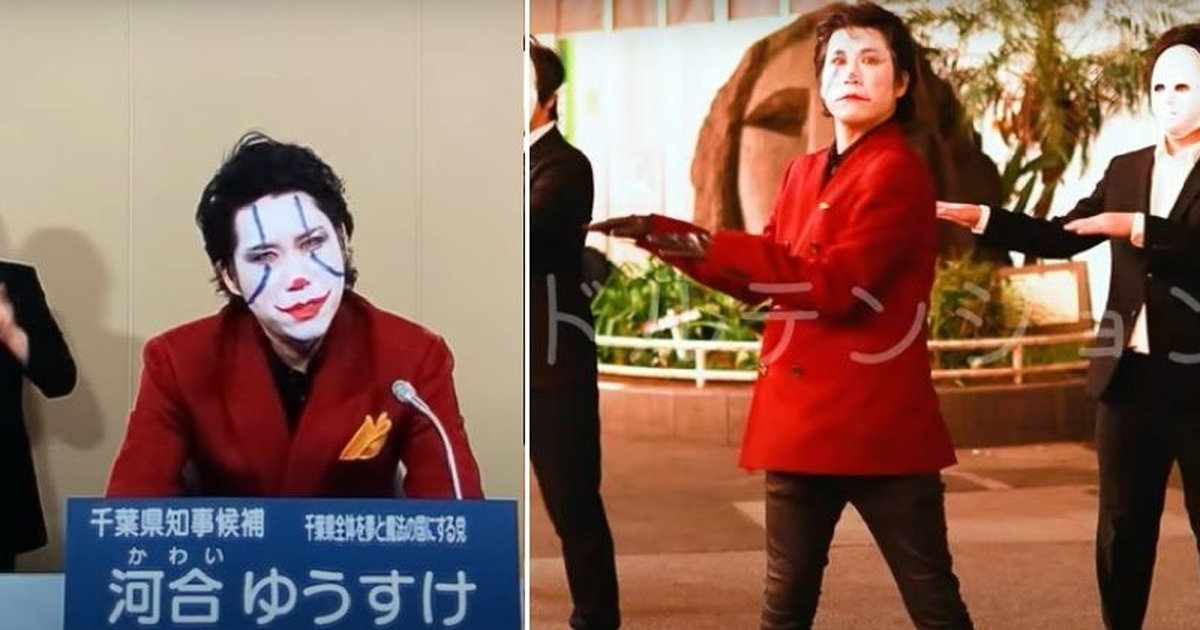8月22日の取引中、市場が安倍首相の重要な講演を待ち望んでいた中、ドルの対通貨バスケットレートが10週間の高値から反落し、9カ月ぶりの安値を付けた後、日本円の対米ドル為替レートは反発した。米国連邦準備制度理事会(FRB)のジェローム・パウエル議長。
最近の円安傾向を受けて、金融市場では東京当局がどのような為替レートで行動するかについての憶測が広がっている。
ドルの対円相場は一時0.22%下落し、1ドル=14万5935円となった。 これに先立ち、先週木曜日、円は1ドル=14万6,565円まで下落し、2022年11月10日以来の円安水準となった。この水準の為替レートは、1ドル=146円に達したため、当局による介入の観測を再び引き起こした。マルクは、東京が初めて円を市場から吸い出すために通貨注入を実施した基準である。 昨年の9月。
米ドルの上昇傾向は依然として強い
8月22日の円高は、日本銀行(日銀)の上田和夫総裁と岸田文雄首相の会談後に起きた。 しかし、上田氏は会談後、会談中に為替変動については話し合わなかったと述べた。
ドルが10週間ぶりの高値を付けた後に下落する中、円も上昇した。 他の主要6通貨バスケットに対するドルの強さを示すドル指数は0.14%下落し、103.2ポイント未満となった。 しかし、この水準は先週金曜日に記録した6月12日以来の最高水準である103.68ポイントからそれほど遠くない。
アナリストの多くは、ドルは依然としてFRBが長期金利を高水準に維持できるとの市場の期待に支えられているため、このドル安は一時的なものに過ぎないと考えている。 この期待は、最近の米国債利回りの力強い上昇傾向に反映されている。
米10年国債利回りは今取引中に一時4.366%に達し、2007年11月以来の高水準となった。
短期金融市場は現在、FRBが来年の利下げを決定するまでに、FRBが年内に0.25%ポイント利上げする可能性が50%近くあると見込んでいる。
今週、ウォール街の投資家は、金曜日午前にワイオミング州ジャクソンホールで開かれた連銀年次総会でのパウエル氏の講演に注目した。 この講演は近い将来のFRBの金利政策についてより明確なシグナルを発するはずだ。
ウェストパックのストラテジスト、リチャード・フラヌロビッチ氏は電話会談で、「パウエル氏が利上げへの扉を開いたままにすれば、ドルの上昇は続くだろう」とドル指数が104の節目を突破する可能性があると述べた。
日本はどのくらいの割合で介入するのか?
元日銀当局者は、日本の当局が介入する可能性がある為替レートについて、1ドル=150円を超えていると述べた。
「当局には正確な制限はありません。 しかし、150円/米ドルのような重要な基準は、政治的理由から重要である」と日本が外国為替市場に介入した当時、日銀外国為替部長だった竹内篤氏はロイターに語った。
竹内氏によると、日本の企業や家計は為替レートの変動を非常に懸念しているため、いつ介入するかを決める際には世論が重要な要素になるという。 しかし、家計が物価上昇に慣れているため、現在では円安に対する懸念は1年前に比べて低くなっている。
同氏は、新型コロナウイルス感染症後の日本の経済活動再開が観光業や国内サービス部門の回復につながる中、円安の恩恵もより明らかになってきていると付け加えた。 「日本では外国為替市場にいつ介入するかは常に高度に政治的な決定だ。 現在、最終決定を下すのは首相だ」と竹内氏は語った。
「円安に対する国民の不満は昨年ほど高くない。岸田氏が対応を迫られる大きなプレッシャーにさらされているとは思わない」と元当局者は語った。 しかし同氏は、円安が加速して1ドル=150円の壁を越えれば、当局が全面的に介入できると信じている。
竹内氏によると、当局は介入する前に、市場が自ら是正することを期待して、時間を稼ぐために警告を発したり、為替レートを修正したりする可能性があるという。 同氏は「たとえ介入がなくても、政策当局者は市場のボラティリティに無関心だと思われることを望んでいない」と述べた。
日本の法律では、政府は金融政策を決定する権限を持っています。 日銀は財務省の代表として機能し、外国為替市場にいつ介入するかを決定します。
JPモルガン・チェースのアナリストらも竹内氏と同様の見解で、日本は1ドル=150円程度の為替レートでのみ介入すると予想している。 JPモルガン・チェースのリポートは「日本の財務省は1米ドル=145円では外国為替市場に介入しないと考えているが、介入の基準は1米ドル=150円程度になるはずだ」としている。

“Web Specialist. Social Media Ninja. Amateur Food Enthusiast. Alcohol Advocate. General Creator. Beer Guru.”