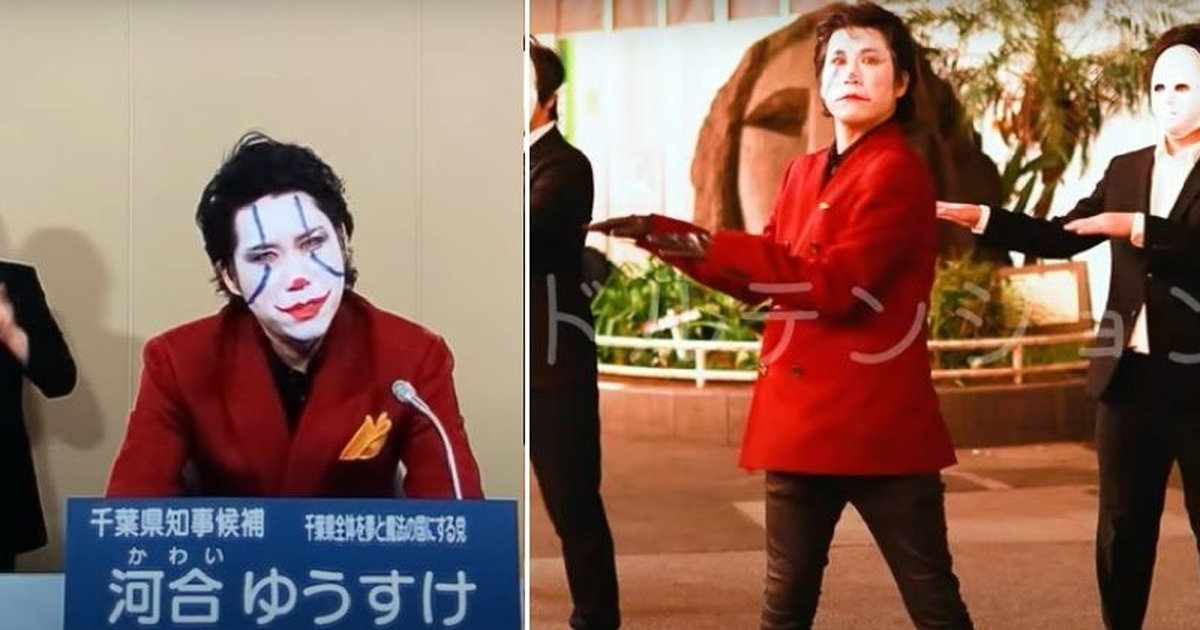アメリカ連邦準備制度理事会(FRB)からの厳しいシグナルを受けて、円為替レートは対ドルで下落を続け、重要な閾値である1米ドル=150円に近づいた。 この展開を受けて金融市場は、自国通貨の為替レートを守るための日本当局による介入が非常に近いのではないかと考えている。
今朝(9月21日)、東京も為替市場への介入の可能性について警告を発した。 日本の松野博一官房長官は、過度の為替レート変動に対処するためのあらゆる選択肢を排除していないと述べた。 松野氏はまた、日本銀行(日銀)が金曜日までの2日間の金融政策決定会合を開催することを期待していると述べた。 – 2%のインフレ目標を達成するために適切な政策を講じる。
松野氏は定例記者会見で最近の通貨切り下げについて問われ、「重要なことは通貨が経済のファンダメンタルズを反映して安定していなければならないということだ」と語った。
同氏は「日本政府は高い危機感を持って外国為替市場の動向を注視し、あらゆる選択肢を排除することなく、それに応じて対応していく」と述べた。
9月20日に閉幕した金融政策決定会合で、FRBはフェデラルファンド金利を5.25~5.5%の間で据え置いたが、今年残りの期間は再度利上げする可能性を残したまま、30%金利の継続を示唆した。より高いレベル。 さらに2024年まで。
FRBのこの困難な中断の後、今朝(9月21日)の円為替レートは一時1ドル=148.4円まで下落し、財務省財政が限界と考えている1ドル=150円の水準からそれほど遠くなかった。 介入します。
松野氏の発言は、日本のトップ金融外交官である神田正人氏の発言と一致している。 神田氏は9月20日、当局は「為替レートが過度に変動し続ける場合にはいかなる選択肢も排除しない」と述べた。
神田氏はまた、日本政府は為替問題に関して米国当局と緊密に連絡を取り続けているとも述べた。 これに先立ち、ジャネット・イエレン米財務長官は、いかなる介入も特定の為替レート水準に影響を与えるのではなく、ボラティリティの低下を目的とすべきだと述べていた。
円安は、日本製品の海外での競争力を高め、日本企業が外貨を国内通貨に交換する際により多くの利益を得ることができるため、日本の輸出業者に有利となります。 しかし、円安は家計の購買力を低下させ、それによって生活費を上昇させるため、日本政府にとって頭の痛い政治問題である。
日本は昨年9月と10月に外国為替市場に介入し、円相場は1ドル=152円近くまで下落し、32年ぶりの安値となった。
円安の影響に対処するという圧力を受け、日銀は7月にイールドカーブ・コントロール(YCC)政策を緩和し、インフレ見通しをより忠実に反映して長期金利の上昇を容認した。
ロイター通信によると、アナリストの多くは現在、日銀が金曜日も非常に緩和的な金融政策を維持すると予想しており、日程表上で上田和夫総裁からの何らかのシグナルに注目しているという。 将来。
日本では、為替政策において決定的な役割を果たしているのは中央銀行ではなく政府である。 したがって、外国為替市場に介入するかどうか、またいつ介入するかを決定するのは日本の財務省になります。

“Web Specialist. Social Media Ninja. Amateur Food Enthusiast. Alcohol Advocate. General Creator. Beer Guru.”